GranEnde:Saga 攻略ガイド【完全版】
ゲーム概要と基本システム
『GranEnde:Saga』は、ドット絵で描かれた重厚な世界観と、古き良きJRPGのゲーム性をベースに、現代的なスキル構成・マルチクラスシステム・戦術構築の奥深さを融合させた高難度ファンタジーRPGです。プレイヤーは、崩壊寸前の世界「アルザリア大陸」を舞台に、伝説の”GranEnde”の真実に迫りながら仲間たちと共に壮大な旅に挑みます。
戦闘はターン制コマンドバトルを採用し、パーティ編成や属性相性、スキル連携などによって一手一手が生死を分ける戦略的な内容となっています。さらに、仲間キャラクターごとに異なる「サブジョブ」選択と、装備品のスキル継承・強化によって自分好みにビルドを組める自由度が、本作の最大の魅力と言えるでしょう。
基本的な進行とシステム解説
- ストーリーパート:章仕立てで進行し、マップ移動・拠点イベント・フィールド探索が絡む。
- バトルパート:行動順が明示されるターン制。スキルにチャージ・詠唱・連携が存在。
- ジョブシステム:各キャラクターに「メイン+サブジョブ」を設定可能。習得スキルも変化。
- 装備強化:武具には固有スキルが付与され、鍛冶屋で素材を使って強化・合成が可能。
本作では、単純に「レベルを上げて進めばよい」RPGではありません。敵のAIが非常に賢く、初見殺しのギミックやバフ・デバフの使い方によって攻略方法が全く変化します。序盤からしっかりとした育成計画と戦術準備が求められます。
攻略チャート:序盤(第1章〜第2章)
第1章「目覚めの谷」
主人公エルスが目覚める谷から物語が始まります。チュートリアルを兼ねた戦闘が続き、回復・防御・属性スキルなどの基礎が学べます。
- 最初の拠点で「防御姿勢(ガード)」の重要性を学ぶ
- エルスの初期スキル「ライトブレード」は光属性であり、序盤のアンデッド系に有効
- 仲間のセリス加入後は、彼女の「キュアライト」でHP管理を安定化させる
最初のボス「アーク・シャドウ」は、闇属性耐性が高いため、セリスに「ヒール+ガード指示」を徹底し、エルスでひたすら物理を叩き込む戦法が有効です。ガードを使わないと開幕2ターンで全滅もありうるので要注意。
第2章「月影の村」
ここからマップが広がり、サブクエスト・サブジョブ選択・装備クラフトが開放されます。
- セリスを「サブ:僧侶」→「白魔法習得」で全体回復を早期取得
- エルスを「サブ:戦士」→「カウンター」+「挑発」でタンク運用強化
- 装備合成で「スティールソード+火晶石」→「フレイムソード」作成
第2章終盤の中ボス「ツンドラビースト」は氷属性の全体攻撃が強力です。火耐性アクセと「バリアウォール」の準備が攻略の鍵です。バフ解除スキル「ディスペル」は序盤でも重要な場面が多く、できればこの章中に1人は覚えさせておきましょう。
中盤(第3章〜第5章):システム理解と構成力が問われる区間
第3章「炎都グレンベルグ」
火山帯の街を舞台に、状態異常と地形トラップの連携戦闘が本格化します。この章で仲間になる「ベルナド」は物理系アタッカーで、斧+反撃スキルに特化しています。
- おすすめビルド:メイン「バーサーカー」+サブ「騎士」→「反撃の構え」+「防御UP」
- 街の鍛冶屋で「炎鉄鉱石」×3を使うと「ブラッドアクス」が解放される
- フィールドに設置された「爆裂花」は、敵にも味方にもダメージを与えるギミック
この章では「ターン制限ミッション」も追加され、数ターン内に敵を撃破しないと全体デバフがかかる場面があります。行動順調整(AGIブースト)や、全体攻撃スキルの習得が重要になります。
第4章「水の聖域」
水属性を中心とした防御型の敵が多く、反射バリア・回復・スリップダメージを組み合わせてくるテクニカルな戦闘が目立ちます。
- 「沈黙」対策を用意:水属性魔術師の「アイスノート」が沈黙付与持ち
- ボス戦では「浮遊」持ちの敵が登場するため、地上特化スキルが効かない
- ヒーラーに「浄化の祈り(全体状態異常回復)」を覚えさせることを推奨
この章で加入する「ユーリ」はサポート特化キャラで、「詠唱短縮」や「スキル再使用」など、戦術の幅を大きく広げてくれます。彼の魔術+セリスの回復構成は、中盤以降の高難度戦で大いに役立ちます。
第5章「砂塵の王墓」
トラップ・連戦・リソース管理といった要素が一気に難度を押し上げてきます。特に「ターンごとの天候変化」や「HP回復を受けるとダメージになるバフ」など、プレイヤーに多角的な判断を強いる構成です。
- 装備スキル「砂耐性」または「消耗抑制」は全員に付けておくべき
- 戦闘前セーブを活用しないと詰みやすいマップ構成
- ボス「無貌の王」は2回行動+状態異常連打+カウントダウン即死攻撃持ち
このあたりから、「ただ強いスキルを使えば勝てる」段階は終わります。バフ・デバフ・ターゲット集中・行動順管理など、フルにシステムを使いこなさないと勝てません。合言葉は“防御こそ最大の攻撃”。
戦闘テクニック・ビルド構築の実践例
本作最大の醍醐味の1つは、キャラごとの役割に合わせたビルド構築です。以下はおすすめの育成例:
| キャラ | メインジョブ | サブジョブ | 運用方針 |
|---|---|---|---|
| エルス | 剣士 | 聖騎士 | 挑発+カウンターで敵を引き付けつつ自己回復 |
| セリス | 僧侶 | 学者 | 回復&MP再生、知識スキルで状態異常もケア |
| ベルナド | バーサーカー | 重騎士 | 一撃高火力型。HPが減っていると火力上昇 |
| ユーリ | 術士 | 吟遊詩人 | 詠唱短縮+支援歌で全体サポート |
どのキャラも単体では機能せず、互いにスキルと行動タイミングを補完し合う構成にすることが重要です。特に中盤以降は「火力があるから勝てる」ではなく、「機能するチームを作れたから勝てる」RPGになります。
終盤(第6章〜第8章):全ての判断が試される激戦の連続
第6章「月蝕の塔」
この章では敵AIの強化、マップギミック、制限付き戦闘などの要素が集中的に登場します。通常攻撃すら封じられる「沈黙結界」「詠唱封印」などを潜り抜け、最上階の中ボスを突破するのが目標となります。
- 状態異常無効装備を2人以上に所持させる
- ボス前に中間セーブポイントがないため、リトライ時は長距離のやり直し必須
- 「詠唱スキップ」系の装備効果が極めて有効
また、この章クリア時に「真・サブジョブ」の条件を満たすことができ、2周目要素の基礎がここで揃います。
第7章「凍界深層」
属性ギミックと行動制御が極まる章。マップ全体が氷の滑走ギミックと定期ダメージで構成され、まともに移動すら困難。戦闘中にも「凍結床」が影響し、移動不能やAGI激減状態に陥ることが多数。
- 耐氷装備・ブーツ系アイテム必須
- 「スリップダメージ無効」のパッシブが大活躍
- 敵の範囲スキル「フリーズドーム」は1ターン以内に解除しないと壊滅必至
ボスの「アーク・フロストドラゴン」は、毎ターン「魔力再構築」を発動し、HP半減からの全体反撃をしてきます。行動順を操作して「バリア→ヒール→バフ→攻撃」の手順を守ることが生存の鍵です。
第8章「大崩壊の地/終末領域」
最終章にふさわしく、過去すべてのギミック・状態異常・連戦・行動制御が襲い掛かる連続マップです。セーブポイント間が長く、装備やアイテムの使い切りが頻発するため、綿密な計画が要求されます。
- 「行動順変更」スキルで常に先手を取る構成を
- HP自動回復や蘇生手段を複数確保しておく
- ラスボスは3形態あり、パーティ構成を途中変更できる貴重なタイミングあり
特にラスボス最終形態は、過去に倒したボスの特性をすべて使ってきます。火力・回復・補助のバランスを崩さずに対応できる柔軟な構築が求められます。
エンディング分岐と条件一覧
| エンディング | 条件 | 特徴 |
|---|---|---|
| ノーマル | ラスボス撃破後、選択肢「力を手放す」 | もっとも無難な結末。後日談あり |
| トゥルー | 仲間全員の信頼度MAX+全サブイベント達成 | 全キャラの未来描写と“真実”が語られる |
| バッド | ラスボスに敗北、または「力を選ぶ」 | 一部ヒロインの喪失。破滅END |
トゥルーエンドの条件は難易度が高く、すべての仲間を正しい順序で育成・支援しないと信頼度が足りません。中盤以降は「会話イベント」もこまめに消化し、選択肢を適切に選ぶ必要があります。
やり込み要素と2周目特典
ゲームクリア後には以下の特典が開放されます:
- 「真サブジョブ」:ジョブごとの隠し上位職。例:僧侶→聖律者、剣士→魔導剣士
- 「強化周回」:敵が強くなる代わりにドロップ率・経験値が2倍
- 「裏ボス討伐」:特定エリアにのみ出現する凶悪ボス(報酬スキル付き)
全実績・全スチル・全セリフ埋めには2周以上の周回が前提となります。周回用の引き継ぎ設定も細かく指定できるため、自分のプレイスタイルに応じた進行が可能です。
▶ Kindle Unlimitedの無料体験はこちら(30日間読み放題)


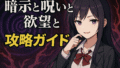
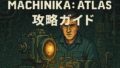

コメント